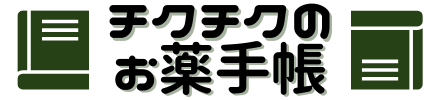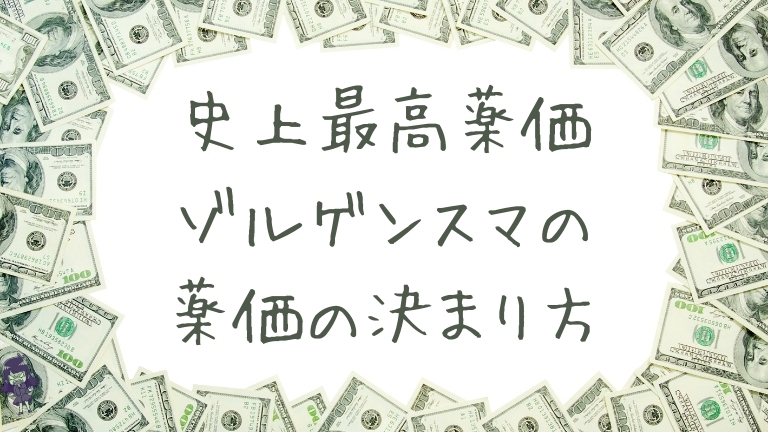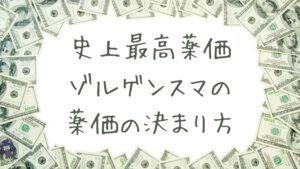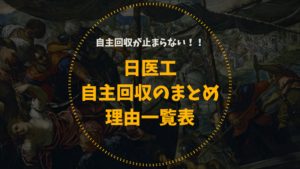ゾルゲンスマって高くない?
どうやって薬価決まったの?
海外はどれくらいの値段で売られているの?

こんな疑問をお持ちではありませんか?
そしてゾルゲンスマって?というそこのあなた
このニュースを覚えてらっしゃいませんか?
凄いですよね。アメリカでは 従来治療では4億円 それを2.3億で治療するのですから、 10年で1億7千万円の削減です。 さらに1回の投薬で治療が完了する薬剤なので、 患者さんの負担もこれまでより大きく軽減できます。 そして 日本でも1億6700万円に決まりました。 ただ、製薬会社勤務の私はこんな疑問を持ちました。ゾルゲンスマはスイスの製薬大手ノバルティスによる薬で、体内に遺伝子を入れて病気を治す「遺伝子治療薬」だ。 脊髄性筋萎縮症は出生10万人あたり2~3人が発症する難病で、発症時期が早いほど重症になりやすい。生後6カ月までに発症する「I型」では、9割が2歳までに呼吸補助が常に必要になるか、死亡するとされる。 治験で15人の患者に投与したところ、全員が2年たっても呼吸補助を必要とせず生存したとの結果が出た。ノバルティスは日本では年間15~20人の患者への投与を想定している。 米国での販売価格は約2億3千万円。従来の治療法を10年続けた場合にかかる医療費約4億円の半額で設定された。ゾルゲンスマは1回の投薬で治療を済ませるため、単価は高くなる。世界で最も高額な薬剤とされる。

こんなに画期的なのに企業へのインセンティブ少なすぎないか?

なんか裏がありそう…計算してみるか!!!
ということで計算してみました…

結論は以上ですが、ここからは詳細を紹介します。

いやいやいやいや
高いでしょ!
もくじ
日米の総医療費比較
 まず簡単に医療費の比較を行っていきます。
現状得られている条件を整理すると以下の通りです。
まず簡単に医療費の比較を行っていきます。
現状得られている条件を整理すると以下の通りです。- 従来治療は10年で4億円。つまり年間平均金額は4000万円
- 新規治療は米国薬価は2.3億円、1回使い切り
- 新規治療は日本薬価は1.67億円、1回使い切り
- 毎年1例の新規患者がいる場合の10年間の総費用を計算

これを元に計算をします。
計算結果
計算結果は以下の通りです。わかりやすく表にまとめております。★スピンラザの場合
 毎年1例新規症例が発症するとして10年間使用した場合従来治療では22億円かかります。
この病は遺伝病なので毎年20人くらい発症してしまうので 22億×20で440億円が日本ではかかっています。 ★ゾルゲンスマの場合(アメリカ) それではゾルゲンスマ(アメリカ薬価)の場合はどうでしょうか。
ゾルゲンスマは1回で治療を済ませるため、使った後は0円です。
これだけでも患者さんのメリット大きいですよね。
毎年1例新規症例が発症するとして10年間使用した場合従来治療では22億円かかります。
この病は遺伝病なので毎年20人くらい発症してしまうので 22億×20で440億円が日本ではかかっています。 ★ゾルゲンスマの場合(アメリカ) それではゾルゲンスマ(アメリカ薬価)の場合はどうでしょうか。
ゾルゲンスマは1回で治療を済ませるため、使った後は0円です。
これだけでも患者さんのメリット大きいですよね。  総治療費は23億円。 やっぱり従来治療より1億円高くなりますね。
毎年20症例に使われた時は 460億円。
20億円高くなっています。
総治療費は23億円。 やっぱり従来治療より1億円高くなりますね。
毎年20症例に使われた時は 460億円。
20億円高くなっています。
やっぱりいい薬ですからね。
アメリカはインセンティブ有りましたね。
適正な価格です。
★ゾルゲンスマの場合(日本)
 では日本はどうでしょうか? 同様に計算すると日本は10年で16億7000万です。 従来治療だと22億円だったので
毎年1例に使われると仮定すると10年で5.3億円。 予想患者数の20例だと106億円削減されることになります。
では日本はどうでしょうか? 同様に計算すると日本は10年で16億7000万です。 従来治療だと22億円だったので
毎年1例に使われると仮定すると10年で5.3億円。 予想患者数の20例だと106億円削減されることになります。【金額小括】 従来治療:440億円/10年 新規治療(米):460億円/10年 新規治療(日):334億円/10年

日本政府は100億以上医療費を浮かせるわけ!
製薬会社は不当に利益を搾取されている可能性がある…
日本での薬価算定ルール
 そうは言っても日本にもちゃんとルールはあります。 ではどの様に薬価が決められたのでしょうか?
内容の詳細は2020年5月13日の中医協の議事録に記載があります。
そうは言っても日本にもちゃんとルールはあります。 ではどの様に薬価が決められたのでしょうか?
内容の詳細は2020年5月13日の中医協の議事録に記載があります。本製品は、脊髄性筋萎縮症を対象とする再生医療等製品です。本製品と効能や投与形態等が類似するスピンラザ髄注12mgを最類似薬とした、類似薬効比較方式(Ⅰ)により算定いたしました。 類似薬効比較方式(Ⅰ)の算定では、本製品を投与することによってスピンラザの投与が不要となる期間を臨床試験の結果等から計算し、その期間に必要となるスピンラザ11本分の薬剤費に補正加算を適用いたしました。 補正加算について、本製品は要件イの新規作用機序であることと、要件ハの治療方法の改善の2つに該当すると判断いたしました。 具体的には要件イとして、脊髄性筋萎縮症を対象とする製品として初めての遺伝子治療製品であり、正常な遺伝子を細胞に直接的に導入するという既存治療とは大きく異なる新規の作用機序を持ちます。 また、原理的には根治の可能性もある新規作用機序であり、臨床上特に有用であると判断し、薬価算定組織で評価されました。 次に要件ハとして、本品による治療で長期間の効果が確認されており、また、治療が1回で終了することや静注であることが患者負担の軽減につながるとして、特に著しい治療方法の改善であることが薬価算定組織で評価されました。 以上のことから、有用性加算(Ⅰ)の50%加算を適用することが妥当と判断いたしました。 さらに、本品は先駆け審査指定制度の対象となっていること等から、先駆け審査指定制度加算の10%加算を適用することが妥当と判断いたしました。 その結果、合計の補正加算率は60%となり、本剤の算定薬価は1患者当たり1億6,707万7,222円となりました 2020年5月13日の中医協議事録ポイントをまとめると以下の4点です。
- 類似薬効比較方式(Ⅰ)
- スピンラザ11本分の薬価で計算(臨床試験から導かれた期間)
- 有用性加算(Ⅰ):50%
- 先駆け審査指定制度加算:10%加算

なんだしっかり計算されているじゃないの?

でも類似薬効がスピンラザ11本に設定された理由を考えると
ちょっと納得がいかないと思う。
ここの設定が最大のポイントなんだ。
スピンラザ11本に設定された理由と、最新の長期フォロー結果
スピンラザ11本に設定された理由は ゾルゲンスマのPⅢ試験の期間が約2年だったため それに相当する11本が設定されています。
これを聞いて、え?って思いませんか?
ゾルゲンスマが2年以上効く可能性は十二分にあるのに
それは度外視したわけです。
チクチク

データがないからね…
どれだけ効果を示しづづけるかは、
これからの追跡調査の結果がが待たれますが
多くの症例が2年後も効果を示し続ける可能性は
発売当初からわかっていたはずです。
実際、すでにP1試験の長期追跡調査は発表されていまして、
その結果部分を引用すると
All patients who received the therapeutic dose have survived and are free of permanent ventilation (mean [range] age at last data cut: 4.8 [4.3–5.6] years; mean [range] time since dosing: 4.5 [4.1–5.2] years). 引用:BMJ:S11 Long-term follow-up of the phase 1 START trial of onasemnogene abeparvovec gene therapy in spinal muscular atrophy type 1

ただ、日本の財務省&中医協がそれを絶対許さないよね。 実際、前述の議事録にも以下記載があります。
松本委員 ただ、ゾルゲンスマについてですけれども、非常に著しく単価の高いという薬剤ですので、今回は脊髄性筋萎縮症という難病の治療薬ではあるものの、H3として費用対効果評価の対象とすることは妥当だと考えておりますけれども、ゾルゲンスマは類薬であるスピンラザと比較しても投与回数が少なく、長期的にはこの類薬よりも費用が削減される可能性が示唆されております。 引用:2020年5月13日の中医協議事録
まとめ
 日本のゾルゲンスマの薬価のつき方がなんかおかしいよ!という話をさせていただきました。 もともとの10年間の市場が440億円。
画期的な新薬を使った場合334億円といった新しい治療の方が儲からないという異常な結果です。 日本は類似薬効に使う薬剤の量をギリギリまで下げることで アメリカと比較して非常に安い薬価をつけることに成功しました。 正直、本来ならば、アメリカの様に高くなるべき薬です。
アメリカと同薬価でも保険に与える影響は年間2億円です。
人口割すると2円に満たない様な上昇です。
もともと希少疾病なので、インパクトは少ないのです。 高ければいいというものではありませんが、希少疾病で、患者数の拡大はそもそも望めない。
それでも、企業努力でノバルティスは画期的な薬を作りました。 にも関わらず従来の市場より少ない金額しか資金回収ができないのならば、
製薬企業の希少疾病の新薬開発モチベーションは落ちてしまうのではないでしょうか?
製薬企業は慈善事業ではなく営利団体です。
リターンが得られない領域には投資したくないというのは当たり前です。 もともとの10年間の市場が440億円。
新薬を使った場合334億円というのはあんまりだと個人的には考えます。
ノバルティスも少なくとも同程度の440億は稼げると見込んで投資を行っていたのではないでしょうか。 実際薬価交渉はかなり難航していました。 医薬品に関わる身としては安すぎると感じています。
それくらい画期的な新薬なのは間違いありません。
安い薬価がついたことで日本における希少疾病薬の開発が遅れることがない様に願ってやみません。
日本のゾルゲンスマの薬価のつき方がなんかおかしいよ!という話をさせていただきました。 もともとの10年間の市場が440億円。
画期的な新薬を使った場合334億円といった新しい治療の方が儲からないという異常な結果です。 日本は類似薬効に使う薬剤の量をギリギリまで下げることで アメリカと比較して非常に安い薬価をつけることに成功しました。 正直、本来ならば、アメリカの様に高くなるべき薬です。
アメリカと同薬価でも保険に与える影響は年間2億円です。
人口割すると2円に満たない様な上昇です。
もともと希少疾病なので、インパクトは少ないのです。 高ければいいというものではありませんが、希少疾病で、患者数の拡大はそもそも望めない。
それでも、企業努力でノバルティスは画期的な薬を作りました。 にも関わらず従来の市場より少ない金額しか資金回収ができないのならば、
製薬企業の希少疾病の新薬開発モチベーションは落ちてしまうのではないでしょうか?
製薬企業は慈善事業ではなく営利団体です。
リターンが得られない領域には投資したくないというのは当たり前です。 もともとの10年間の市場が440億円。
新薬を使った場合334億円というのはあんまりだと個人的には考えます。
ノバルティスも少なくとも同程度の440億は稼げると見込んで投資を行っていたのではないでしょうか。 実際薬価交渉はかなり難航していました。 医薬品に関わる身としては安すぎると感じています。
それくらい画期的な新薬なのは間違いありません。
安い薬価がついたことで日本における希少疾病薬の開発が遅れることがない様に願ってやみません。
希少疾病の領域で薬価削減を行うことは長い目で見れば患者のためになりませんし、
あまりにも新薬メーカーと研究者に対するリスペクトが欠けていると言わざるを得ません。 日本の薬価は明らかに安すぎます。
追跡調査の結果を反映して薬価の再算定をするべきです。