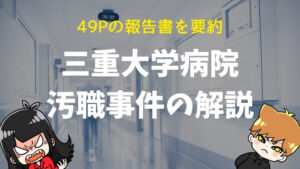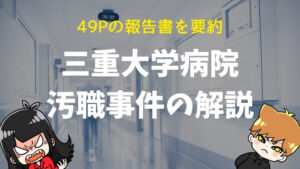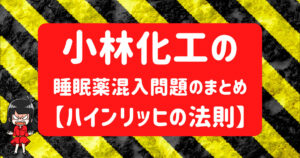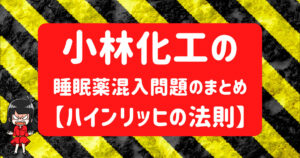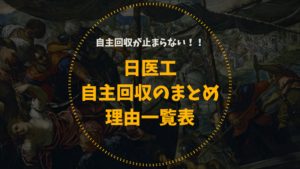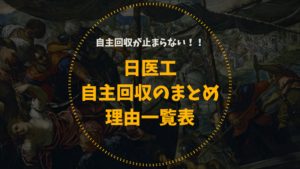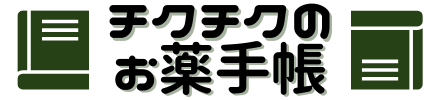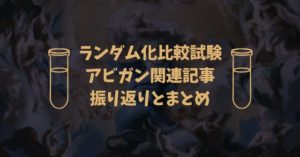2019年の年末に
医薬品卸が談合を行ったという
ニュースがありました。
そのあとCOVID-19 関連で
それどころではなくなったので
忘れられつつありますが、
ここで一度振り返るとともに
問題点と薬を取り巻くお金の話を紹介します!
以下日経記事の引用です。
独立行政法人「地域医療機能推進機構」(JCHO、東京・港)発注の医薬品の入札を巡り、談合を繰り返した疑いが強まったとして、公正取引委員会は27日、医薬品卸大手4社の本社など関係先について独占禁止法違反(不当な取引制限)容疑で強制調査を始めた。
検察当局への刑事告発を視野に調査を進める。
公取委は検察への刑事告発を視野に調査を進める強制調査の対象は、医薬品卸最大手のメディパルホールディングス(HD)傘下のメディセオ(東京・中央)、アルフレッサHD傘下のアルフレッサ(同・千代田)、スズケン(名古屋市)、東邦HD傘下の東邦薬品(東京・世田谷)。
公取委は押収した資料の分析と関係者への事情聴取を進め、年間受注規模が数百億円に上るJCHO向けの医薬品納入を巡る談合疑惑の実態解明を本格化させる。
関係者によると、メディセオなど4社は2018年にJCHOが発注した医薬品の一般競争入札を巡り、事前に落札業者を決めて受注調整を図った疑いが持たれている
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52657690X21C19A1MM0000/
正直これを聞いた時、
常日頃医薬品卸と関わる
私の感想は
 ドチク子
ドチク子え?これ刺すの?
こんなの日本全国
どこでもやっているし、
卸だけじゃなくて
製薬会社、取引先、国、
業界全体の責任じゃん!!!
という感想が率直なものでした。
(批判はあるかもしれませんが)
なぜ業界全体の責任と感じたのか。
医薬品取引を取り巻く価格と合わせて、
この内容に切り込んでいきます。
本記事のポイント
・一般の方でも医薬品取引に関わる価格に詳しくなれます
・一般の方でも2019医薬品卸談合問題の背景がわかるようになります。
医薬品の3つの薬価とリベート


医薬品取引を紹介するにあたり、
紹介するものは4つです。
- 薬価
- 仕切価
- 納入価
- リベート
この4つが理解できれば
ボヤッと問題が見えてきます。
薬価
薬価は非常に身近なものですよね。
病院や薬局でもらう薬の値段です。
これは国が原価算定や類似薬効比較等の方法で
決めています。
国が100円と決めたら、
誰が何と言おうと薬局&病院は
100円で売らなければなりません。



ちなみに消費税分も
含まれています!
国民全員が保険を使う日本では、
製薬会社が各々価格設定してしまうと
システムの崩壊を招く可能性があります。
システム崩壊を防ぐために国が制定しています。
すこし穿った見方をすると
自由競争の大事な要因である
価格決定の自由を
日本で商売する製薬会社は奪われています。



まぁこれはどうしようもありませんけどね。製薬業界と国で協力して保険システム維持しようぜって感じですね。



とは言っても
2015年からは少しやりすぎ
ではあるよね



その辺りの話は
関連記事で紹介しています!
ご確認ください!




※ここから紹介する仕切価や納入価の
値引率は談合のあった
2019年当初の値引率で記載しています。
現在は2021年の薬価規定を受けて
縮小傾向にあります。
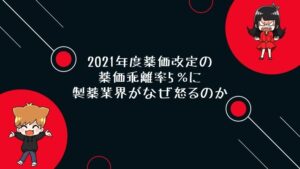
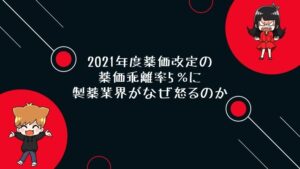
仕切価
続いて仕切価です!仕切価は
製薬会社から医薬品卸に販売する時の価格です。
新薬だと大体10~5%
ジェネリックだと30%以上
薬価から引かれた形で設定されます。
会社によって差も大きいので
一概には言えませんが、
私が勤めている会社は91%くらいに
設定されていますので9%引位ですね。
少し調べると平均は94%弱程度なので
弊社は仕切価自体は安いのかもしれません。
そのぶんリベート(後述します)は少ないです。
基本的には仕切価の売上が
製薬会社の売り上げになります。
ですので弊社の場合、
薬価100円の薬を卸すと
91円の売り上げになります。



ここから各種経費を
引いたものが利益です。
納入価
納入価は
医薬品卸が医院や調剤薬局に売る値段です。
理想は仕切価よりも
高く売らなければなりません。
薬価100円。仕切価91円ならば、
99~92円の間で売ることが
出来れば仕切価との差分が
医薬品卸の儲けになります。
仮に95円で売れた場合は95-91円で
1錠当たり4円の売り上げです。
ここから経費が引かれます。
おわかりいただける通り
非常に薄利多売の世界です。
逆に調剤薬局や病院は
納入価が低くなればなるほど利益が生まれます。
薬価-納入価が売り上げになりますので、
この場合だと1錠当たり5円です。
薬価:100円、仕切価:91円、納入価95円の場合だと
- 製薬会社売上:仕切価=91円
- 医薬品卸売上:納入価‐仕切価=4円
- 薬局病院売上:薬価‐納入価=5円
となります。
卸と薬局&病院は
売上を取り合っている関係です。
納入価は調剤薬局、病院の経営者と
卸MS(マーケティングスペシャリスト)の間の
交渉で決定します。
パワーのある経営者が相手だったりすると
未だに新薬20%引、後発品50%引という
クリニックも存在します。
これだと当然卸は赤字です。
しかしながら卸間で競争させる上、
製薬業界に内在するシステム上の問題により
納入価の平均は90%くらいになっています。
前述のとおり仕切価の業界平均は94%程度です。
業界として約4%の赤字経営です。
さらにここから人件費や輸送費等の
経費が引かれるのでさらに赤字になります。



この赤字を埋めてきたのが
リベートです。
リベート
リベートは売り上げに対する払戻金です。
会社が各々きめています。
ざっくりいうと
具体的には100円の薬を100錠売れば
1000円製薬会社から医薬品卸に払います
こんな感じの契約です。
契約方法は色々ありまして、
製薬会社と医薬品卸売会社の間で
目標と達成時のリベートが
毎期毎期、握られます。
100円の薬を100錠売れば
1000円のリベート契約条件だと
- 薬価:100円
- 仕切価:95円
- 納入価90円



こんな赤字の販売でも
- 総薬価:10,000円(100円×100錠)
- 製薬会社売上:9,500-1,000円=8,500円
- 医薬品卸売上:-500+1,000円=500円
- 薬局&病院売上:1,000円
となり売上赤字が消えます。
リベートを払いながらも
製薬会社の利益率は良かったので
卸も医療機関も黒字にして
win-win-winの関係を成り立たせてきました!
長らく製薬業界はリベートを使って
歪んだ販売形態で成り立ってきました。



医療機関の取り分が
多すぎるのか、
製薬会社の取り分が
多すぎるのかは
議論が別れますが、
その調整役として
リベートは
機能してきたわけです。
リベートシステムの問題と是正による影響と歪み


しかしながらこのリベートシステムは
製薬会社にとってみれば
間接的な価格操作システムになる訳です。
どうしてもシェアを取りたい薬がある場合は
リベートを多く出せば大きく値引きが出来て
病院や調剤にメリットがある形に誘導できます。
国はそれを防ぐために
- 値引き目的の過大なリベートを禁止
- 処方権を持つ病院と調剤を分ける
- 安売りされている薬の薬価を下げる
こんなことをして
製薬会社の利益を奪い対応してきました。
結果、製薬会社は売上ではなく
医薬品卸の処方推進行動に
リベートを払うように変化したり、
リベートそのものを
見直すようになってきました。



また利益を出せず
十分なリベートを
出せない会社も出てきています
すると医薬品卸はリベートでは
十二分に利益が得られなくなってきました。
こうなると医薬品卸は
赤字を防ぐため納入価を上げて
対応するしかありません。
そういった背景もあって近年納入価を上げるべく
血のにじむような努力が行われてきました…
しかしながら長期にわたり
異常に安い納入価格を味わい
利益を上げてきた医療機関は
当然、同じ価格で納めるように迫ります。
会社としては上げざるを得ませんが、
他の会社の担当者が売り上げのために
赤字覚悟で安い値段を出せば、
売り上げが大きく減ってしまいます。
さらに、卸の担当者には
売り上げ目標があります。
担当者レベルで見れば安売りしても
売上はほしい訳です。
さらにもともと利益率1-2%の
薄利多売で成り立っている業界です。
黒字圏内でも1円の安さで
他社に奪われれば
大きな損失になってしまいます。
そうなったときの逃げ道が談合でした。
幸か不幸かわかりませんが卸担当者同士は
担当の医療機関が主催するイベントや
医療機関の待合室で顔を合わす機会も多いため
相談の機会は豊富にあります。





あそこは手を引くから
こっちはちょうだい



OK!
高めの値段だしときます。
こっちはお願いしますね
こんな感じで
少ない利益を確保するために相談してきた訳です。正直日本中でやられていたと思います。
両方とれなくても、
相談しておけば既存の利益は守れますからね。
今回の事件は規模が大きかっただけです。
もちろん談合自体は取引違反ですし
罪は罪なのですが
- リベートありきで黒字化するような販売形態を迫っていた製薬会社
- リベート是正により収益方法の転換を迫り収入源を奪った国
- 背景を理解せず、納入価上昇に対応せず卸にプレッシャーをかける医療機関の存在
こういったさまざまなプレッシャーを受けた
市場の歪みを医薬品卸が受け入れて、
適応していった結果、
効率的だったものの一つが談合だった訳です。



こういった背景を考えると
医薬品卸だけを責めるのも
違う気がしませんか?
最後に


なにより国はこういった
産業構造の歪みを認識していたはずです。
長期にわたり放置していたにもかかわらず、
このタイミングで主要4社を
つるし上げるのは少々ひどい様に感じます。
割愛しましたがリベート是正だけじゃなく
長期の薬価引き下げも要因の一つですからね。
いわば国によるマッチポンプです。
事件後の対応から
国のメッセージを考察するならば、
談合再発予防のために取られた談合防止策は
短期的に医薬品卸の利益を奪うものです。
自由競争により
短期的には利益が減りますし
納入価は下がります。
納入価が下がれば
薬価を下げることが出来ます。
製薬業界の抵抗によって
医薬品の薬価が削れなくなってきたので、
医薬品卸をターゲットにすることで
薬価をさらに下げ
財源を確保するつもりなんでしょう。
正直製薬業界としては
たまったもんでは有りませんね。



自由取引の原則から行くと談合は決して許されることではないけれどね



それでも国の作戦の犠牲になっている様にがどうしても感じてしまいます。
不祥事系の関連記事