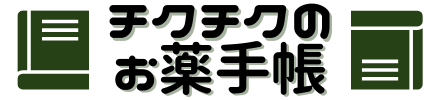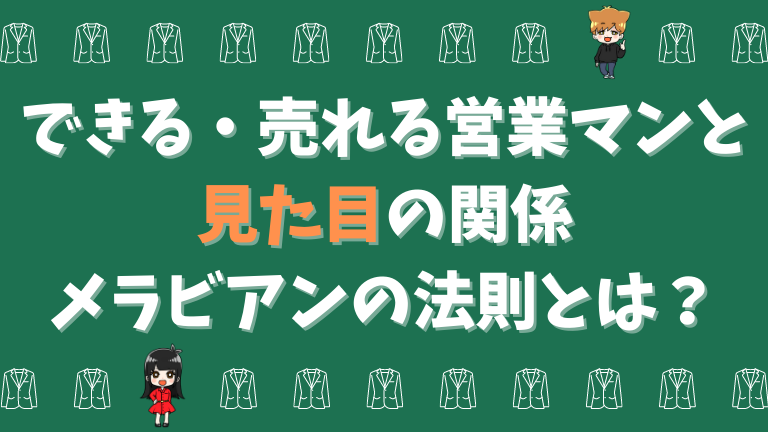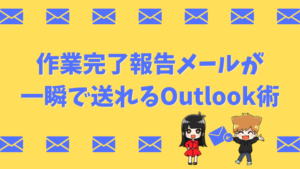【結論だけ知りたい人向け】
先にデメリットを短く伝えてから、
最後をポジティブな内容で締めることで、
印象がよくなりやすいことが
心理学の研究でわかっています。
(ゲイン・ロス効果/ピーク・エンドの法則)
 チクチク
チクチクあなたはこのように
自信を持って答えられるでしょうか?
第一印象が採用の有無を決める新製品の場合、
この順番の違いが意外と大きな差を生みます。
どちらがデメリットを最小化し
メリットを最大化する話法でしょうか?
本記事ではゲイン・ロス効果、初頭効果、
確証バイアス、ピーク・エンドの法則を紹介し
この問題をクリアにしていきます。



悪いことは
言わなければいいんじゃ…
ケケケ
結論:いいことと悪いことは「悪い話→いい話」の順番で話すべき
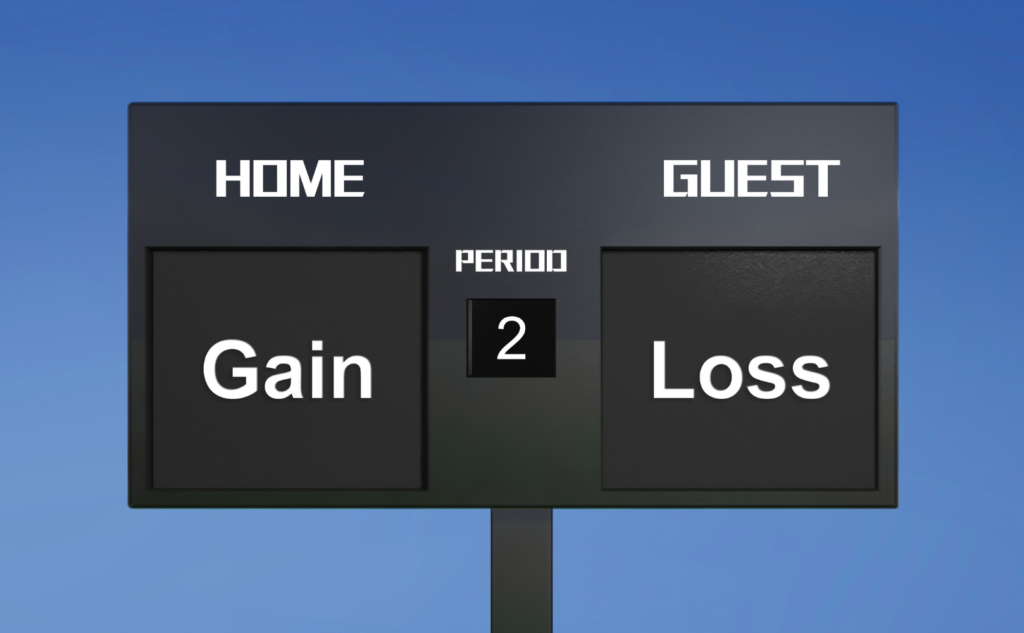
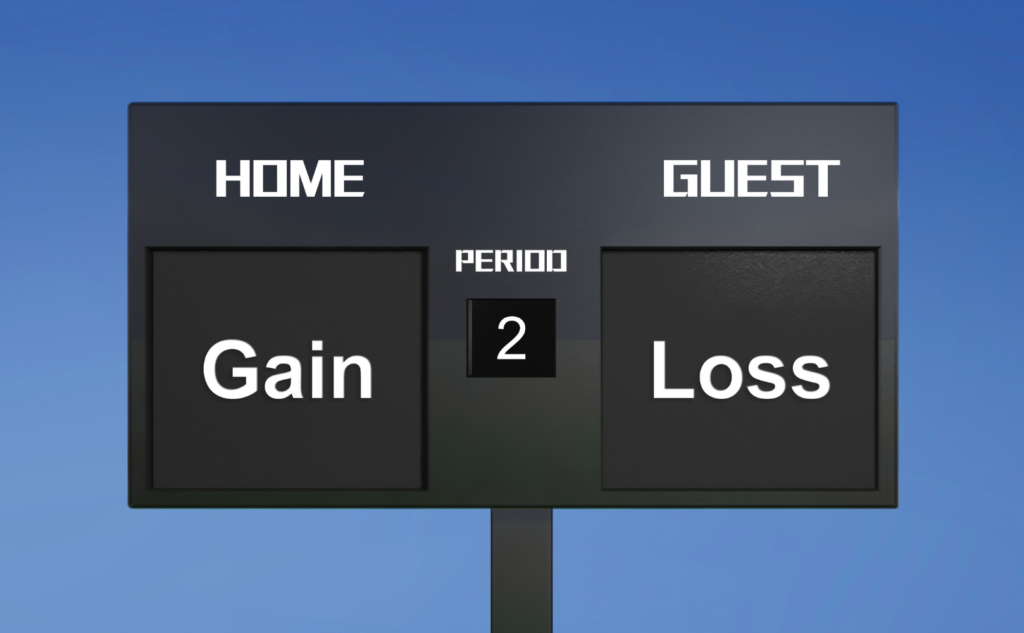
悪いこと→良いこと
この順番で話しましょう!
- ゲインロス効果
- ピークエンドの法則
理由には、この2つの心理学的効果が関連します。
これらの効果について詳しく紹介します。
ゲイン・ロス効果
まずはゲイン・ロス効果です。
アメリカの心理学者、
Aronson & Linder(1965)による
魅力度評定実験により証明された効果です。
▶️原著:Gain and loss of esteem as determinants of interpersonal attractiveness
この効果は、
ただ褒めるよりも少し否定的な評価をして
後で好意的な評価をした方が
評価が高くなるというものです。
少々難しく聞こえますがなんてことはありません。
単なるギャップ萌えです!!
落としてから上げるだけです!
不良が猫に傘さしてあげててキュンとした!!ってやつです。
人間にはマイナスからプラスへ
プラスからマイナスへ触れた時に
必要以上に良い評価をする
性質があります。
実験をすっごく簡単にいうと
自身に対する評価をこっそり聞いてもらい
評価者への印象をスコア化する…というものです。



余談ですがミネソタ大学の
女子学生80人に行われました。
この時の評価者は評価を
4つのどれかにするように決められています。
- ネガティブ-ポジティブに途中で変化
- ポジティブ-ポジティブと変化なし
- ネガティブ-ネガティブと変化なし
- ポジティブ-ネガティブに途中で変化
そして実験後に
+10:非常に好き
0:無関心
-10:非常に嫌い
この条件で、評価者を被験者(女子大生)に
評価してもらいました。
結果は以下のとおりです。
- ネガティブ-ポジティブ:+7.67(SD:1.51)
- ポジティブ-ポジティブ:+6.24(SD:1.42)
- ネガティブ-ネガティブ:+2.52(SD:3.16)
- ポジティブ-ネガティブ:+0.87(SD:3.32)
面白いですよね。
一貫してポジティブな評価よりも
ネガティブな評価を混ぜた方が印象も良いですし、
逆にポジティブからネガティブに落とすと
ずっとネガティブな場合より嫌われます。
(正確には無関心と評価されます。)



これは異性関係にも
使えるテクニック…
ゲインロス効果を実験
実感を持ってもらうために
少し実験をしてみます。
どちらの方が良い印象を受けますか?
・痛いですが、効果はある薬です。
・効果はありますが、痛い薬です。
前者の方が良い印象を
受けるのではないでしょうか?
言っている内容は同じなのに不思議ですよね。
これがギャップ萌えゲイン・ロス効果です。
この効果は
ギャップが大きくなるほど
強くなりますので、
文章の前後の文章を強調すると
よりわかり易くなります。
・とても痛いですが、効果は強い薬です。
・効果は強いですが、とても痛い薬です。
修飾するとより差が生まれて見えます。
実際に現場で使うのは
デメリット→メリットの形ですので、
「痛いですが、効果がある薬」という
文章のゲインロス効果を最大化すると
・痛いですが、効果がある薬です。
・痛いですが、とても効果がある薬です。
・とても痛いですが、最も効果がある薬です。
下にいくほど差が大きくなりますので、
最後の文章が最も効果的になります。



ただ、
ここには落とし穴があります。
後述します。
ポイント
先にデメリットを言って、
その後メリットを話す。
そのギャップが大きければ
良いイメージも大きくなる。
初頭効果に注意
ゲイン・ロス効果は
ただ褒めるよりも
初めに少し否定的な評価をして、
後で好意的な評価をした方が
相手に対する評価が高くなると紹介しました。
否定的な話は
少しでなければなりません。
沢山話してはいけません
「とても痛いですが、最も効果がある薬です。」これがゲイン・ロス効果が強いと紹介しましたが、実は否定が強すぎてマイナスの効果が発生しています。
そのマイナスの効果を初頭効果と言います。



初頭効果は最初のイメージがあまりに良かったり悪かったりすると、その印象が強すぎてゲイン・ロス効果がうまく働かなくなることを表しています。



実際に先程の組み合わせでTwitterでアンケートを取ってみたところ
「とても痛いですが、最も効果がある薬です。」は2番手です。
ゲイン・ロス効果が最大限に働き
最もイメージが良くなるかと思いきや、
とても痛いという言葉の悪い印象が強すぎて
初頭効果により足を引っ張られています。



あまりにもデメリットが強烈だと
ゲイン・ロス効果が働かなくなってしまいます。
あまりにもデメリットが強烈だと
ゲイン・ロス効果が働かなくなってしまいます。



フォロワー増えたので
再計測してみました!
医療系のフォロワーが増えたので
効果を求める効果が強くなり
逆転していますね!
それでも問2から問3の
上昇幅は縮小しています。
これは初頭効果による
マイナスと言えそうですね!
補足:確証バイアス
似た様な事象として
確証バイアスというものもあります。
これは最初のイメージに引っ張られて
自分に都合の良い情報しか
集めなくなることを言います。
最初のイメージが悪すぎると、
悪いイメージの情報を支える情報を
どんどん集める様になってしまいます。
いきなりデメリットを前面に押して、
新製品を紹介すると
確証バイアスが強く働き
思う様にいかなくなる可能性があります。



最初は他の話題で、心理的な障壁を下げる必要があるでしょう。
ピーク・エンドの法則
ゲインロス効果と合わせて
知っておくべき法則として
ピーク・エンドの法則も紹介します。
ピークエンドの法則は、
行動経済学者のダニエル・カーネマンが
1999年に発表した法則です。
人はほとんどの経験を
最も感情が高ぶった瞬間(ピーク)と
最後の印象(エンド)で判断するという内容です。
つまり営業で紹介した情報の
ほとんどは判断材料になりません。
顧客の心を動かした瞬間と
最後が大きな判断材料となっています。
顧客の心を動かすであろう内容は
あたりをつけて紹介することは可能ですが、
確実に心を動かすとなると困難を極めます。
人の心ということもあり、
少々コントロールが難しい部分です。
対して最後の印象は
紹介側がコントロールする事が可能です。
最後の部分にメリットを持ってきたり、
ポイントを再掲する事で
ゲイン・ロス効果と
ピークエンドの法則の重ねがけを狙えます。
さらにゲイン・ロス効果により
顧客の気持ちも動き易くなり
ピークとエンド両方の効果が
得られる可能性も上がります



製薬会社の説明会では難しいけど、
一般向けの講演で最後に
感動的な曲を流す講師は
これを狙っているらしいよ。
ポイント
最後のまとめではポジティブな好印象を!
まとめ


ポイント
①先にデメリットを言って、その後メリットを話す。そのギャップが大きければ良いイメージも大きくなる。
②初頭効果を抑えゲイン・ロス効果を最大化するためにはデメリットは許容できる範囲である事が重要
③最後のまとめではポジティブな好印象を徹底的に狙っていく
再三にはなりますが、この3つがポイントです。
営業の際にも、
言いにくいポイントを許容できる様に修飾し、
かつメリットを大きく見せる事で
ゲイン・ロス効果を最大限利用し、
最後のまとめではできるだけポジティブな印象を
演出する事が最も効果的ではないでしょうか。



なお医薬品の紹介時に「とても」や「非常に」と言った主観を伴う修飾語を使うと、ルールに抵触してしまう可能性があります。あくまで事実ベースでゲイン・ロス効果を利用しましょう。
【関連記事】