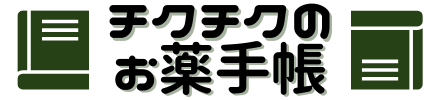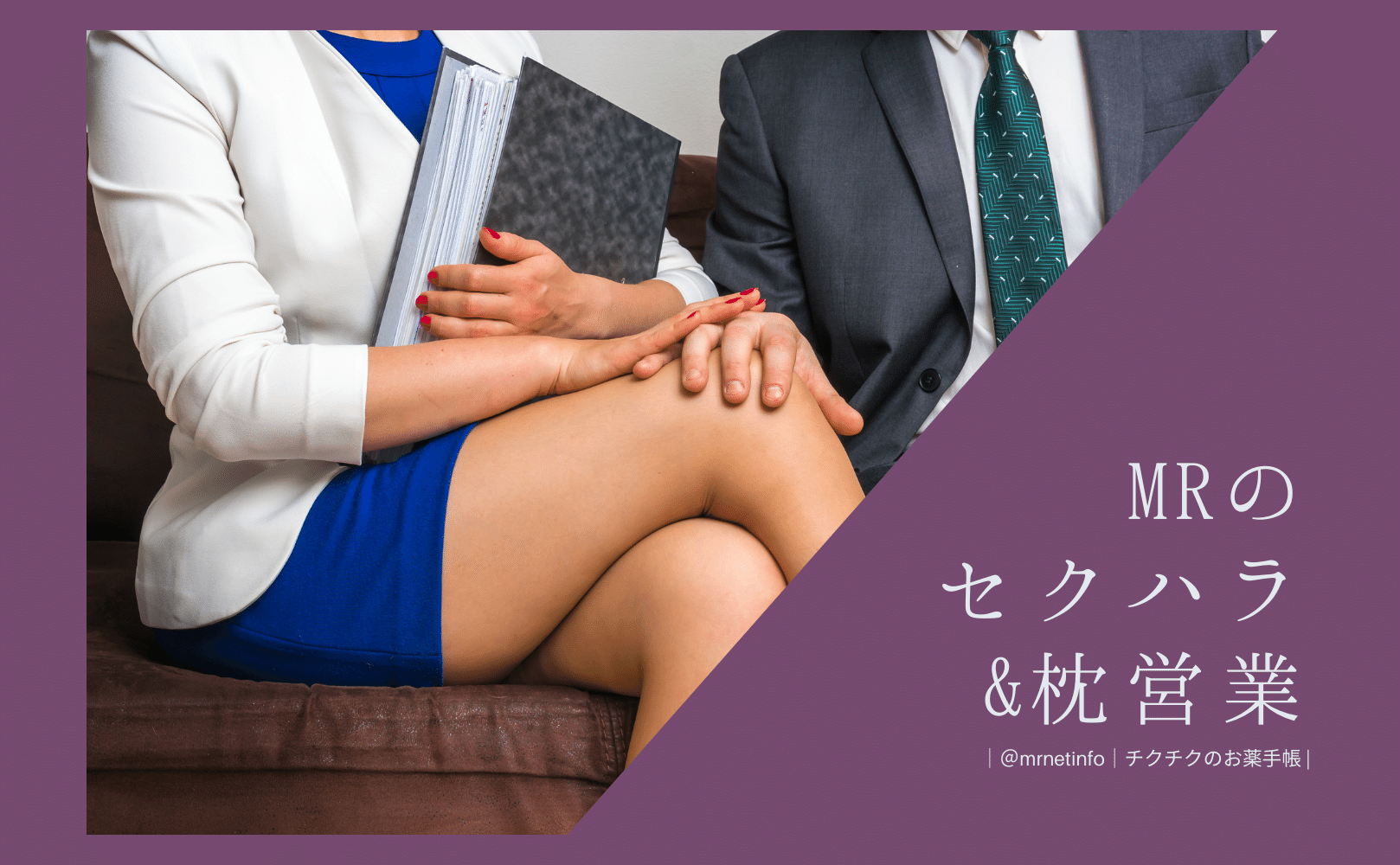みなさんこんにちは。
 チクチク
チクチク正直カラオケは
好きなチクチクです。
過去本ブログでは、
現在から30年前の曲を5曲以上、持ち歌として用意しておこう
という“歌って盛り上げる側”の
カラオケ戦略をお届けしました。
記事はコチラ↓
ただ、こういう声もあるはずです。
- 「そもそも人前で歌うのが無理なんだけど…」
- 「持ち歌を用意する以前に、マイクを持つこと自体がつらい」
- 「それでも会社のカラオケには顔を出さないといけない」
そこで今回は、
「新人がカラオケで“歌わない”で乗り切る方法」
上記にフォーカスします!
- 歌わなくても評価を落とさない立ち回り
- 失礼にならない断り方
- 歌わない代わりに“何で場に参加するか”
をセットで整理していきます。
「歌わない=悪」ではありません。
「何もしない=マイナス」なだけです。



このスタンスを軸に、具体的に見ていきましょう。
なぜ新人はカラオケで悩むのか?&結論


私も顧客や上司とのカラオケでは
悩みに悩んだので
この気持ちには覚えがあります!



当時を思い出しながら
整理してみます
「カラオケで歌わないとダメ」と感じてしまう3つの理由
新人・新入社員がカラオケでモヤモヤする理由は、
だいたい次の3つに集約されます。
- 「歌わない=ノリが悪い」と思われそう
- 上司や先輩の本音が読めない
- 断り方がわからない(空気を壊しそうで怖い)
ポイントは、
- 上司や顧客には
「歌ってほしい」という人もいれば、 - 「そこまで強制するつもりはない」
という人もいます
正直、会社や上司ごとに
“ローカルルール”が違います。
なので本質的には場合わけして
対策を立てなければいけません。
が!



本記事はそれでもできるだけ歌わなくていい方法に最大限フォーカスを当てて執筆していきます!



何がなんでも歌いたくない人のための記事だもんね
結論:歌わないのはアリ。ただし「歌わないなら何で参加するか」が重要
この記事の立ち位置はシンプルです。
- 歌わない選択=アリ
- ただし
- スマホいじり
- 無表情
- リアクションゼロ
この状態は、「感じ悪い新人」に見えやすく、
さすがに損です。
歌わない代わりに、
「何で場に貢献するか」を決めておく



これが、評価を落とさないための最低ラインの考え方です。
本記事でわかること
この記事でわかることは以下のとおりです
【この記事でわかること】
- カラオケで新人が見られているポイント
- 歌わない新人が絶対に避けたいNG行動
- シーン別の歌わない立ち回りの具体例
- どうしてもつらいときの“参加しない”戦略
前回の
「30年前の持ち歌5曲」記事と
合わせて読むと、
- 「歌う戦略」
- 「歌わない戦略」



両方を自分の体質に合わせて選べるようになります。
職場カラオケの「暗黙ルール」とカラオケハラスメント
敵を知れば百戦危うからず…
まずは、カラオケの危険ポイントを
しっかりみていきましょう
上司・先輩はカラオケで何を見ているのか
多くの上司・先輩が見ているのは、
だいたい次のあたりです。
- 歌唱力
⇒ ほぼ見ていない - 見ているのは
- 場の空気を壊さないか
- 人の歌にちゃんとリアクションしているか
- 誘いに対する態度が極端に冷たくないか
つまり、「歌がうまい新人」より
「一緒にいて気持ちいい新人」か否か?
チェックされているのはこれが全てです。
ここの心構えを間違うと
危険ポイントすなわち地雷を
踏み抜きます!



この辺りは飲み会と全く同じね


カラオケハラスメント(カラハラ)とは
一方で、最近よく言われるのが
カラオケハラスメントです。



カラオケまで…
ハラスメント???
たとえば、
- 明らかに嫌がっている人にマイクを押しつける
- 歌わない人をしつこくいじる、からかう
- 「歌わないなら来るな」「ノリ悪いよね」と責める
こういった行為は、
ハラスメントに該当する可能性が高い行動です。
「歌わないといけない場」ではありません。
「みんなで楽しむ場」のはずです。
この記事は、「ハラスメントに耐えろ」と言いたいわけではありません。



その前提で
“歌わない側の立ち回り”を
整理していきます。
歌わない選択が許される場面と、リスクが高い場面



それでは具体的にみていきます
歌わなくても問題になりにくいシチュエーション


以下のような場では、
歌わなくても評価が下がりにくいです。
- 大人数のカラオケ(二次会で20人以上など)
- 部署や年齢がごちゃ混ぜの「なんとなくの二次会」
- 歌わない人がそもそも一定数いる
- 上司や先輩が歌うのを楽しみたい雰囲気が強い
こういう場では、
歌わなくても
- リモコン操作
- ドリンク・フードのケア
- 拍手・手拍子・合いの手
上記を目立つようにを
しっかりやっていれば、
「ちゃんと参加している人」
として見てもらえます。



ただ歌わない以上
ここでは全力でアピってください!
歌わないと浮きやすいシチュエーション


逆に、次のような場面は注意ゾーンです。
- 3〜4人程度の少人数カラオケ
- 明らかに「新人の歓迎会」として設定された会
- 上司が「一曲だけでいいから」と何回も念押ししてくる
- 「歌ってなんぼ」の風土が強い部署
こういう場では、
“まったく歌わない”のは浮きやすいです。
- 「1曲だけ保険で歌う」
- 「それも難しければ、後述する“断り方+貢献”を最大化する」
など、一段ギアを上げた
立ち回りが必要になります。



このケースはどう考えても
完全に断るのはリスクが高いので
覚悟を決めてください!
ここだけです!
そもそも参加しない選択が正当なケース


さらに、次のような場合は
無理をして参加する必要はありません。
- メンタル的に非常につらい時期
- 体調が悪い、通院が必要なタイミング
- どう考えてもパワハラ気味の飲み会が予定されている
そういう場合は、
- 一次会までは参加して二次会を辞退する
- その日だけは最初から欠席する
など、自分の心身を守るための
“欠席戦略”も普通にアリです。
コチラ、詳細を後述いたします。



できるだけ歌わないために
そもそも会に参加しないという
君子危うきに近寄らず
戦略を取りましょう
歌わない新人が絶対に避けるべきNG行動
このセクションでは
参加する場合のNG行動を4つ挙げています!



これだけは絶対避けましょう!
NG1:スマホいじり・無表情・リアクションゼロ


歌っていようが、歌っていまいが、
これだけはやめておいた方がよいものがあります。
- 歌の最中にずっとスマホを見ている
- 拍手もなく、表情も動かない
- いじられても「…」と無反応
これは、「歌わないから」ではなく
「感じ悪いから」
印象が落ちます。
歌わないなら、
「リアクション」と「気配り」のギアを少し上げる



これが最低限のマナーです。
NG2:「行きたくない感」を前面に出す


- 「行きたくなかったんですけど…」
これをわざわざ口に出す - 行きの移動中からずっと不機嫌
これも場の空気を冷やしやすい行動です。
本当に嫌なら「参加しない」方を選ぶべきで、
- 行くと決めたなら
「その時間だけは役割を演じきる」
くらいの割り切りがあった方が楽です。



覚悟は全てに通じます…


NG3:毎回、直前キャンセルで逃げ続ける


毎回、ギリギリで、
- 「やっぱり行けなくなりました」
を繰り返すと、信用そのものが削れていきます。
欠席するなら、
- 予定が見えた段階で早めに伝える
- 理由は長々と言わなくてよいが、ひと言そえる



この2点を守るだけで
印象はかなり違います。
NG4:歌わないのに飲み食いだけ全力


- 一切歌わない
- リアクションも薄い
- でも飲み食いは誰よりもしている
これはさすがに
マイナスポイントが大きいパターンです。
歌わないなら、
- 料理を取り分ける
- ドリンクをみんなに聞いて回る
- 歌っている人を盛り上げる



などで「場の手伝い」にまわる意識を持つと、印象が逆転します。
シーン別:歌わずに乗り切る具体的な立ち回り
方針が見えてきたところで
よりイメージしやすくなるように
より具体的にみていきます!
一次会のうちにやっておく“小さな布石”
二次会がカラオケになりそうな雰囲気のときは、
一次会のうちに軽くこう言っておくと楽です。



布石打ってしまいましょう!
「自分、本当に歌が苦手で…歌うより盛り上げ担当の方が得意なんですよ」
これだけで、
- 「歌わない=ノリが悪い」ではなく
- 「この人は盛り上げ担当なんだな」
と、周囲の期待値を少し調整できます。
なにより、自分で口に出した以上
覚悟が決まります…
覚悟は全てを解決します!



やはり覚悟
覚悟は全てを解決する…
カラオケ到着直後の席選び
歌わない前提で動くなら、
座る位置も地味に重要です。
- ドリンクバーや呼び出しボタンに近い席
- リモコンやタブレットに手が届きやすい位置
- 出入口側で、動きやすい場所
こういう場所に座ると、
- オーダー役
- 曲入れ役
- 盛り上げ役



として自然に動きやすくなります。
歌わない代わりにできる「3つの貢献」
歌わないときの基本セットは次の3つです。
- ドリンク・フードのケア
- グラスが空いている人に「次どうします?」とひと言
- フードの残りをさりげなく取り分ける
- リモコン・曲入れ役
- 「次、何か入れましょうか?」と声をかける
- 先輩が迷っていたら「これどうですか?」と補助
- 拍手・合いの手・タンバリン
- サビで手拍子を入れる
- 曲が終わったら必ず拍手+ひと言
- 「これ、懐かしいですね!」
- 「この曲めっちゃ好きです」



“場を回している人”
これに徹するのです...
マイクが回ってきた時の、失礼にならない断り方


どうしてもマイクが回ってきたときのために、
テンプレを2〜3個持っておきましょう。
- パターン1:素直に“苦手宣言”+代わりの役割
「すみません、本当に音痴で…。
場を壊しそうなので、代わりに盛り上げ担当やってもいいですか?」 - パターン2:一次会の布石とのセット
「さっきもお話した通りで、歌は本気で苦手で…その代わり、注文と盛り上げは全力でやります!」



「何もしないための言い訳」ではなく、
「別の形で貢献する宣言」にしておくのがポイントです。
それでも強く勧められた時の最終ライン


- 何度も何度も「一曲だけ!」と押される
- 明らかに断りづらい空気になっている
このときは、次の2パターンです。
- 「保険で用意していた1曲」を割り切って歌う
- 心身的に本当にきつい場合は、正直に限界を伝える
「すみません、本当にこういう場が苦手で…どうしても歌うのは難しいです」
このレベルの一言を出してもなお、しつこく強要されるなら、
それはあなたの問題ではなく“場の側の問題”です。



これは今の時代ではハラスメントの粋だよね



とはいえ顧客相手にこれやったら
色々と終わると思うから
オススメはしないけどね…
どうしても1曲だけ歌う場合の「最低限の準備」
ここからは、「基本は歌わないけれど、保険として1曲だけは準備しておきたい」人向けです。
歌わない方針でも「保険の1曲」は持っておくべき理由
- 少人数カラオケになったときの逃げ場になる
- 「一曲だけ歌って、あとは盛り上げ役に徹する」という選択肢が取れる
- 「まったく歌えない人」と「一応1曲だけ持っている人」では印象がかなり違う



歌うかどうかは当日決めるとしても、“歌える状態”を作っておくだけで、心の余裕が変わります。
選曲
選曲は上司や顧客の年齢に合わせて選びましょう!



理屈とオススメはコチラの記事を参照してください!
音痴でも致命傷にならない歌い方のコツ
- サビだけは前もって口ずさんでおく
- 音程よりも「リズム」と「表情」に集中する
- 途中でミスっても、顔をしかめず笑ってごまかす
「うまく歌う」ではなく
「気まずくならないように歌う」
これくらいのマインドで十分です。
大事なのは…
覚悟です!
全力で歌い切ってください!



魂を震わせてください!
それは伝わります。
本当にカラオケがつらい人のための「参加しない」戦略
冒頭で
君子危に近寄らず戦略を詳しくみていきます。
メンタル・健康面が限界のときは、無理をしない
- 睡眠不足が続いている
- メンタル的にかなりすり減っている
- 通院が必要なタイミング
こういったときは、
カラオケに行ってもプラスはほぼありません。
一次会参加+二次会辞退、
あるいはその日は丸ごと欠席
と言った選択も勇気です。



苦手&経験が少ないことを
悪いメンタル+フィジカルで
乗り越えられるわけがありません!
角を立てない断り方の言い回し集
- 「明日どうしても朝イチで外せない予定があって、今日は一次会までにさせてください」
- 「今ちょっと体調を崩していて、長時間は厳しいので…」
- 「通院の関係で夜遅くまでは残れなくて…」
長々と言い訳を重ねるより、
短く・はっきり・一度だけ言う方が、逆に印象は良かったりします。



まじで無理なんです感を出していきましょう!
自分なりの「参加ライン」を決めておく
- 年に何回までなら無理なく付き合えるか
- どのパターンの飲み会には参加するのか
- どこから先はきっぱり断るのか
このあたりを
自分の中で先に決めておくと、
毎回悩まずに済みます。
これはどんな人も一度は
考えておくといいと思います。
それでも理不尽な圧が強い場合の相談先
- あからさまな
カラオケハラスメントが続く - 「行かないと評価を下げるぞ」
といった発言が出てくる
こういう場合は、
- 信頼できる先輩
- 人事・労務
- コンプライアンス窓口
などに、とっとと相談してしまいましょう!



行政の相談窓口もあるので
一度眼を通しておくと
良いと思います!
上司・先輩の本音と、長期的なキャリアへの影響
とは言っても歌わないと…長期的に評価に影響があるんじゃ…
こういう恐怖感を持っている人も多いと思います!
でもこれを感じれている人は大丈夫です!
「歌うかどうか」より「一緒にいて気持ちいいか」
多くの上司の本音はこんな感じです。
- 「歌うかどうかは正直どっちでもいい」
- 「一緒にいて気持ちが良い人かどうかは、なんとなく見ている」
つまり、
- 歌がうまいかどうかより
- 人の歌をちゃんと聞けるか
- 空気を読んで動けるか
このあたりが長期的な信頼につながっていきます。



要は気遣い力をみられているに過ぎません!
新人時代のカラオケ経験が後々まで効いてくる理由
カラオケはあくまで「職場コミュニケーションの一場面」にすぎません。
ただ、
- 上司の意外な一面が見えたり
- 他部署との距離が急に縮まったり
あとで振り返ると、
「あのときのカラオケがきっかけで…」
という話も意外と多いものです。
どんな事柄にも
メリット&デメリットがあります!
大事なのは
「歌う・歌わない」ではなく
「どう付き合うか」を自分なりに決めておくことです。
まとめ:歌わない自由と「場に参加する」責任を両立させる
最後に、この記事のポイントを簡単にまとめます。
- 「歌わない=悪」ではない
→ ただし「何もしない=マイナス」になりやすい - 歌わない新人が見られているのは
→ 歌唱力ではなく「リアクション」と「気配り」 - 歌わない代わりにできる3つの貢献
- ドリンク・フードのケア
- リモコン・曲入れ役
- 拍手・合いの手・タンバリン
- どうしてもつらいときは
→ 一次会まで/欠席/相談という“撤退ルート”も用意しておく - 長期的に効いてくるのは
→ 「一緒にいて気持ちいい人かどうか」という印象
そして、「歌わない戦略」だけだとどうしても詰む場面もあります。
そのときの保険として、
前回の記事で紹介した
「30年前の持ち歌を用意しておく戦略」
コチラを組み合わせておくと、
かなり戦いやすくなります。
- 基本戦略:この補足記事の「歌わない立ち回り」
- 保険戦略:前回の記事の「歌うための30年前、持ち歌」
自分の性格や体力に合わせて、
この2つをミックスして使ってもらえればと思います。



カラオケが苦手な新人さんが、
少しでも肩の力を抜いて働けますように。